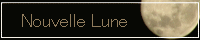空を浮かぶ雲のように、今の気持ちはぷらぷらしてる。
「───ねーぇー、ゆめって、なに?」
遠い空を見上げながら、自分が本当に浮かんでいるような浮遊感を感じながら、なにげなく口にした。
「私」
結構真剣になにげなく口から出た言葉を、隣りに座ってる相棒は実に呆けた返事を返してきたので、少しだけムッとした。
「ちーがーうー! 夢だよ、ゆーめ!」
「だから、私」
「まだ寝ぼけたこと言うか」
「寝ぼけてないじゃない。だって、私だもん」
寝転がってるから悪いんだ、しっかりと相棒の顔を見て言わないと駄目だ、と判断した私は上半身を起こして隣の相棒を見つめる。
すると、相棒は実に満足げな顔をして私を見つめていた。
「よく出来ました」
「……ちゃんと顔見て、話をしたかったのね…?」
「さすが相棒。ちゃんと解ってるじゃない」
「だったら、遠回しな言い方しないで、はっきりと言葉にして言ったらどうなのよ…」
はっきりすっぱりと、面と向かって言ってくれればこっちだってムカッすることもないし、逆にこういう気分の悪い状態を招かなかったと思う。それなのに、彼女は清々しい笑顔でこっちを見るもんだから、私が抱いていた「ムカッ」を柔和させてしまうんだ。
「……」
「で?」
柔和されてしまった私の「ムカッ」は、居場所を失って「失笑」に変わる。
今までトゲトゲしかった自分を、相棒に包まれてしまったもんだからなにげなく自分の居場所もなくしてしまったようで、彼女から目をそらしたら、聞かれた。
「で? …って?」
「貴女にしてみれば、珍しく直球じゃないのね」
ころころと、なにが楽しいのかおかしいのかこっちにはまったく解らないのに、彼女は笑った。
「………呆れてたのよ、あんたの天然すぎる性格に!」
「それで?」
「…そ、それでって…?」
「その私に、なにか言いたいこと、あったんでしょう?」
まるで、神父だ。
懺悔を待つ、神父。
にこにこした顔で、私を見つめて、ちゃんと私の話を聞こうとしている。
「……あんたと話すと、いっつも遠回りするから嫌なのよ」
「あら。それは心外」
「どうして」
「直球続きじゃ、疲れるでしょ?」
「…はぁ?」
「一直線をずーっと見つめ続けるなんて、無理じゃない。道の端に、楽しいことや面白いことが転がってるのよ? ずーっと先を見続けるなんて難しいわ」
「だから、遠回りしろって?」
「そうよ。たまには息抜いて、周りを見渡すのも必要なことよ」
「そうだけど…」
「私、夢、って、そういうものだと思うの」
「はぃ?」
「だから、夢ってなに?って話だったでしょう?」
相棒は、先ほどの神父顔したまま空を見上げた。
さっきまでの私のように。
こいつは、ずるい。
穏やかな顔をして、やっぱり、きちんとちゃんと私の話を聞いてるから。
「ね、遠回りって、いけないこと?」
「…いきなりなによ」
「さっきの話の続きよ」
「息抜きの話?」
「そうそう」
「……遠回りは、嫌」
「あら、やっぱり直球で率直な意見だこと」
「だって当たり前じゃない。向いてる先に、自分の夢があるんだよ? 遠回りしてる暇あったら、全速力で夢に向かって駆けてるっちゅーねん」
「…確かに」
「でしょ?」
「でも、…疲れない?」
「………それ、さっきも言われた」
「だってー、貴女の生き方すっごく疲れそうなんだもの」
「馬鹿ねー。ちゃんと給水場ぐらい作るわよ?」
隣で呆れたような笑顔を称えている彼女に向かって私も言ってやると、なにが面白いのか、またしても笑い始めた。心外だ。言われたから言い返したのに、しかも、自分では言い切り返しだと思っていたのに、笑われるなんて。
くすくすと笑う相棒のましゅまろみたいな笑い声が、ふわふわとした雲に染み込んで、もう一回り大きくなる。少なくとも、私の目にはそう見えた。
「給水場か…、それ、良いね」
「立ち止まる…、わけにはいかないけど、やっぱりちょっとぐらい息抜きしなくちゃ」
「でも、景色を堪能できない」
「…景色?」
「ゴールは夢、途中途中に給水場を設けても、…今まで自分が通ってきた道を全部素通りしちゃうでしょう? もしかして、綺麗なお花が道ばたにあったかもしれない。…そういう美しい景色を逃しちゃうわ」
「景色見ながら走ったら、全速力じゃないでしょ」
「別に全速力で走る必要もないと思うけど?」
「……ふむ。そのために、遠回りが必要ってこと?」
「だって考えてもみて? 自分が歩いてる道って、一本だけなの?」
「…う」
「それって反対に可愛そうなことだと思う。一本しかない道を一人でひたすら走り続けるのは疲れるでしょう? たまに回り道をして、時にはひなたぼっこでもして、そうそう、昼寝なんてしても良いわねー。太陽の光は体にとっても良いんだし」
そよぐ青い風に吹かれるのは、瑞々しい緑。
紅い太陽によって色づけられた黄色の光が、真っ白な自分を照らす。
心を開放して全ての色を持つ虹色の地球に抱かれて、無限の夢を見るの。
「ね、とっても素敵じゃない」
まるで自分のことのように語った世界の「色」は、彼女の全てを構成しているように感じた。
彼女は自由奔放で、本当に「白」という言葉が似合う。
昔、どうして自分を「白」にするのか?と、聞いたことがあって、その時も、彼女はけらけらと笑いながら、「何色にでもなれる要素を誰だって持ってるからよ」と、そう言ってのけた。
ときどき面白いことを言うのは、昔から変わってない。
「……素敵だけど、遠回りは嫌よ」
でも、昔からそういうところが、あまり好きではなかった。
空を見上げた彼女を視界から弾くように俯くと、視界から排除したはずの彼女の明るい声が聞こえた。
「もー、まだ頭が固いのね、貴女は」
呆れる音色に、思わず感情が高ぶった。
なにも知らないくせに。
私のことなんて、これっぽっちも理解してないくせに。
「だってそうじゃない! 自分の夢を掴むのは、自分なんだよ? 自分が努力しなければ、そんな不可触なものなんて手に入れられることが出来ないんだよ?」
欲しくて欲しくて頑張っても、手に入れられなかったら自分が可愛そうだ。
頑張ってきた自分が可愛そうだから、常に一生懸命に「路」を求める。誰だって、そうやって生きてきてる。
それなのに、
「うん、そこまでして欲しいものなの?」
と、彼女はとんでもない言葉を言ってくれた。
思わずぽかん、と開く口。
「…な、あ…え…!?」
「不可触だからこそ、たくさんの夢を夢見ても良いんじゃないの? そしたら、それのどれかが手に入るかもしれないじゃない」
自分は「夢」を手に入れるために産まれてきたのに、彼女はそれをあっさりと否定してしまった。
「うーんと、言ってしまえば、道は一本じゃないんだよってこと」
「……」
「ちゃぁんと、遠回りする道や、逃げ道だって用意されてる。それに、もしかしたら貴女の未来は一つじゃなくて三つや四つに増えてるかもしれないんだよ? それを、今から一つにしちゃうっていうのは、走る楽しみが減ってると思うなー?」
「……そんなことない」
「そうね。貴女がそんなことない、って思うのなら、そうだと思うな」
「…もー! さっきから否定したり、肯定したり、一体なんなのよ!」
「しょうがないじゃない、それが私なんだから」
まるで、そう言われたのがとても嬉しいように彼女は笑う。
「…それで? 貴女は、どうしたいの?」
「え…?」
「聞いて欲しいんでしょう? 私はそのために、来たんだから」
「さすが相棒」
「任せて、相棒」
二人で、冗談半分に笑い合うとトゲトゲとした気持ちが、消える。
すぅーっと心臓に染みいる彼女の声が、心臓から飛び出した棘を一本一本消しているような感じ。
「───苦しいの」
「生きてること?」
「うん。…今は頑張ってるけど、なんかこのまま無様に生きてるっていうのもなーって思って」
「ふぅん」
「もったいないと思う?」
「ちょっとだけね」
「どうして?」
「諦めちゃったら、おしまいだから」
「…諦めてない、って…強く言えないのも、苦しいものだね」
「いつになく弱気だね。なにかあった?」
「ううん。特に。…でも、今までずーっと全速力で走って、戦ってきた分、今すっごく苦しい」
「疲れちゃったのね」
「……うん」
「じゃ、やめちゃえば?」
「…はぃ!?」
「やめちゃえば良いのよ。そうしたら、苦しくなくなる」
「確かにそうだけど…」
「けど?」
「なんか、終わりにしちゃうのももったいない、っていうか…」
「うん」
「悩んでるっていうか…、煮え切らないっていうか…、遠回りするぐらいなら、諦めたいかな…、とか…」
「じゃ、続ければ?」
平然と、さっきから私のことを肯定したり、否定したりする相棒。
そんな彼女の姿が、自分のように見えて、少しだけ笑った。
「自分」をしっかりして、「目標」をしっかり見据えないとふらふらしちゃうんだね。
自分でふらふらしてればザマないや。
「なぁに?」
「…いや、…私も今、そうやって自分のことを肯定したり、否定したりしてるなーって思ったらおかしくて…」
「夢に迷っちゃって自分を見失っちゃったわけね。いつも同じ「夢」の中にいれば誰だって迷うことはある。その中で、自分がどう生きていくか。どうやって、その中で生き抜いていくか、っていうのが大切なのよ」
まさに、そうだ。
自分に迷って、閉じこもって、一人で夢と現実のギャップを知って、馬鹿みたいに「孤独」を感じてた。
「…そっか。だから、気持ちがふらふらしてるんだ」
「そうそう」
「頭でっかちに考えすぎ、…なのかな、もしかして…」
「もしかしなくても、そうだと思うよ?」
そっか。そうだね。
立ち止まって後ろを振り返れば、そこには今まで歩いてきた「路」があるわけで。
そこには、私に関わってきたたくさんの人間がいる。「自分」しか見えていなかった。自分こそが支えられてる、って思ってもみなかった。
思い上がりも良いところだ。
「あら」
「あらあら?」
「ぷっ」
二人で顔を見合わせてみると、なんだ、自然に笑えた。
あんなに悩んでいたのに、普通に笑える。
「うーん、なんか、少しすっきりした…、かな?」
「そ。それなら良かった」
「…私、もう少し馬鹿になる」
「遠回りぐらい、受け入れられるぐらいの馬鹿で良いわよ」
「そうね」
そして、もう一度遠くの空を見上げた。
この先なにが待ってるか解らない空。
そんな空を見つめていると、自分が本当にちっぽけだ。
だから、今を、本当に、本当に大切に生きよう。
時には泣いて、少し立ち止まって。
愛されているのが解ってるのに、「私は一人」なんて思う。
そんな負の自分がいて。
それでも、私を見てくれる人がいる。
優しい言葉を掛けてくれる友人達もいる。
ひっそりと見守りながら心配もしてくれる尊敬している両親もいる。
いつもながらに思うこと。
気付けば誰もが私を見てる。
気付けば、誰もが私を支えてくれている。
こんなちっぽけな自分に、エネルギーを注いでくれる。
自分がどんなに幸せだったか、思い知る。
だいじょうぶ、だいじょうぶ。
一人じゃない、ことがどれだけ心強いか。
笑顔を返してくれるということがどれだけ嬉しいか。
私は幸せ者です。
「──貴女の夢は、なに?」
遠い意識の中で、囁かれた相棒からの言葉は私の心臓に染み込んで、体中を駆けめぐって、ほんの小さな灯火になっていた私の「夢」に光を与えた。
大きく灯した「夢」の光。
消えかけていた灯火。
やる気さえあればなんだって出来る。
命、ある限り、人は「夢」を追いかけることが出来る。
それがどんなにも幸せなことか。
今、こうしている間にも世界中の「夢」が消えている。
命と共に消えた「夢」は、行き場を亡くす。
けれど、行き場を亡くした「夢」は、集まる。
ふわふわと流れ着いた「誰か」の意志に同化して、その人の「光」になる。
それが、「希望」になる。
人間一人一人の「希望」が全部集まれば、「平和」になる。
「光」とはそういうもの。
「人間」とは、それほどまでに可能性を秘めている生物。
今は、解る。なぜ、彼女が地球を、「虹色」と言ったのか。
それは、さまざまな色を灯す全ての「夢」が詰まっているからだ。
「己」を信じろ。
全ての力を秘めているのは、「自分」しかいない。
さぁ、立ち上がれ。目を覚ませ。
「私は、いつでも傍にいるよ。貴女の先に、貴女の中に───」
────私は、絶対に手にする。貴女という名の「夢」を。
「────…みのり…?」
目を覚ますと、目にいっぱい涙を溜めた母がいて。
少しだけムッとしている父がいて。
そして、斬り続けてきた手首に真っ白な包帯が巻かれていた。
それから、…「相棒」の写真が視界の端に見えた。
「…みのり…?」
「夢を見たの。姉ちゃんの夢…」
「…ゆめが、みのりの夢に出てきたの?」
「あのね、姉ちゃん、私の夢になってた」
「え…?」
「夢を持って死んだ人間は、夢という光になれるんだって、姉ちゃんが、そう教えてくれた」
「…みのり」
「二人ともごめんなさい。私、受験も、生きることも、ちゃんと頑張るよ。だから、もう泣かないで…────」
私は、人から見れば、ちっぽけな人間です。
つまらない人間です。
けれど、ここで立って生活していることに誇りを持ってます。
これだけで、いい。
もう、これだけで良いんです。
気付いたときに誰かがこちらを見ていてくれている。
それだけで良いんです。
だからお願いです。
私に、もう少しだけ頑張る力をください。
ここで、くたばってなんて、いられないんです。
───たった「一歩」を踏み出す勇気と、生きる力をください。
-おわり-
るーこから頂いた、2006年の年賀小説です。
みなさんは、どんな事を考えましたか?
私は直接不躾ながらも彼女に言わせて貰ったので、
今ここで書く事は、多く表せなくて。
皆さんがそれぞれ、この話を読んで思う事。
それが大切なんじゃないかなぁと、思いました。
るーこ、年賀小説ありがとう!
そして、こんなヤツだけど、これからもよろしくね><; るーこのサイトはこちらから↓