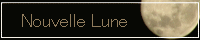彼女が、家にいるということ。
すぐそばにいて、笑ったり困ったり……といろいろな顔を見せて。
……そして、必ず俺を見てくれる。
これは、ほかのどんなヤツにもしてもらえないことだし、俺以外のヤツが見れることじゃない。
わかってる。
それは、わかってるんだ。
だけどやっぱり俺は我侭で……貪欲で。
いくら彼女に貰っても、それでも足りなくて求めてしまう。
もっと、俺だけを――……と。
俺だけを、欲しがってくれればいいのに、と。
彼女の瞳に映るほかの男を、消してしまうだけの薬があったら――……俺は、何に代えても手に入れようと、もがくかもしれない。
「先生?」
温かい手のひらが頬に当たって、ようやく瞳が開いた。
ここにある、温かくて柔らかい存在。
すべてを和ませて、すべてを包み込んで。
そして、すべてを許してくれるような、優しい眼差し。
そのどれもこれもが欲しいのに、手が、声が、出なかった。
……我侭なモンだな。
常に触れていたいのに。
欲しくて欲しくて、堪らないのに。
……なのに、彼女から動いてほしくて。
「…………」
やっぱり我侭だな。俺は。
少しだけ不安げな彼女から視線を外すように瞳を閉じると、小さく自嘲が漏れた。
「……何かあったんですか?」
ほらみろ。
俺のせいで、彼女が苦しむ。
簡単に想像できるのに、俺は何度となく過ちを繰り返す。
彼女に追いかけてほしくて。
彼女にねだってほしくて。
――……俺という人間すべてを、彼女に欲してもらいたくて。
まさに、子どもと同じだ。
彼女の気を惹くためならば、きっと躊躇せずになんでもするだろう。
たとえ彼女を傷つけることになっても、俺はそうしてしまうかもしれない。
「……最低、だよな」
「え……?」
「俺って……」
自分の考えを知らない、澄んだ瞳。
それを捉えたまま、言葉が漏れた。
……俺がこんなこと思ってるって知ったら、幻滅するかもな。
だけど、彼女にこうして心配してもらえることが、すごく嬉しいんだ。
まぁ、そう思っているからこそ、やっぱり自分はひどいヤツなんだろうが。
「……そんなことないもん」
「ありがと。でも、慰めて――」
「そんなっ……! 慰めなんかじゃなくて、私は本当にそう思ってます!」
再び閉じた瞳が、すぐに開いた。
心配そうな顔で、不安そうな瞳で、まっすぐにこちらを見ている彼女に、嘘偽りなど微塵も感じられなかったから。
きゅっと服を掴み、じぃっと瞳を合わせたままの彼女。
……参ったな。
「せ……んせ……?」
もたれるように身体を預け、両腕で彼女を包む。
その途端、鼻先に広がる甘い匂い。
彼女が動くたびに、頬に当たる髪。
……そして。
心底安心する彼女の温もりと――……優しい声。
……すべて、俺だけのものにできればいいのに。
独占って言葉は、まさにこのためにあるんだろう。
愛しい女のすべてを、自分だけのものにしたがる愚かな男のために。
「……俺のこと、抱いて?」
「っ……」
瞳を閉じて唇を耳元へ寄せ、囁くように息をかける。
少し掠れたような自分の声が、今の自分の気持ちを含んでいるようで少しおかしい。
「っ……え……」
自嘲気味に笑うと同時に、彼女がぎゅうっと抱きついてきた。
彼女に回していた腕との間にわずかな隙間が生まれ、思わず焦る。
驚いて彼女を見ると、なんとも――……つらそうに、眉を寄せてしっかりと瞳を閉じていて。
……参ったな。
そんな顔されたら、今さら言えなくなるじゃないか。
これまで押し込めてきた沢山の我侭と欲を、我慢するための言葉が。
「……どうしたんですか?」
ようやく上げてくれた彼女の瞳だが、変わらず切なそうだった。
こんな顔をさせているのは、俺のせい。
だけど、彼女がこうして心配してくれるというのが、不謹慎ながらも嬉しくて。
……ごめん。
伝わるかわからない言葉を、瞳を合わせて思うしかできない。
「そんな顔……しないで」
ひたり、と彼女が頬に手のひらを寄せ、いかにも彼女らしい心配そうな顔を見せた。
……その言葉は、俺が言わなきゃいけないのに。
いつも、そうだな。
彼女は、俺よりも先に俺がしようとしていることをしてくれる。
有難いけれど。
嬉しいけれど。
だけど――……やっぱり自分が情けなくも思えてくる。
……でも。
同時に、こうも思う。
やっぱり、俺には彼女がいなければダメなんだ、と。
「私が……そばにいます」
「っ……」
ね? と続けて小さく首をかしげた彼女に、瞳が開いた。
……この子は。
「っ……! 先生……」
「……俺だって、そばにいるよ」
顎を片手で掴むように捉えてから、唇を合わせる瞬間。
小さく、そうひとことだけ口から漏れた。
2005/6/17